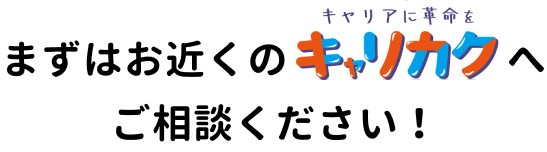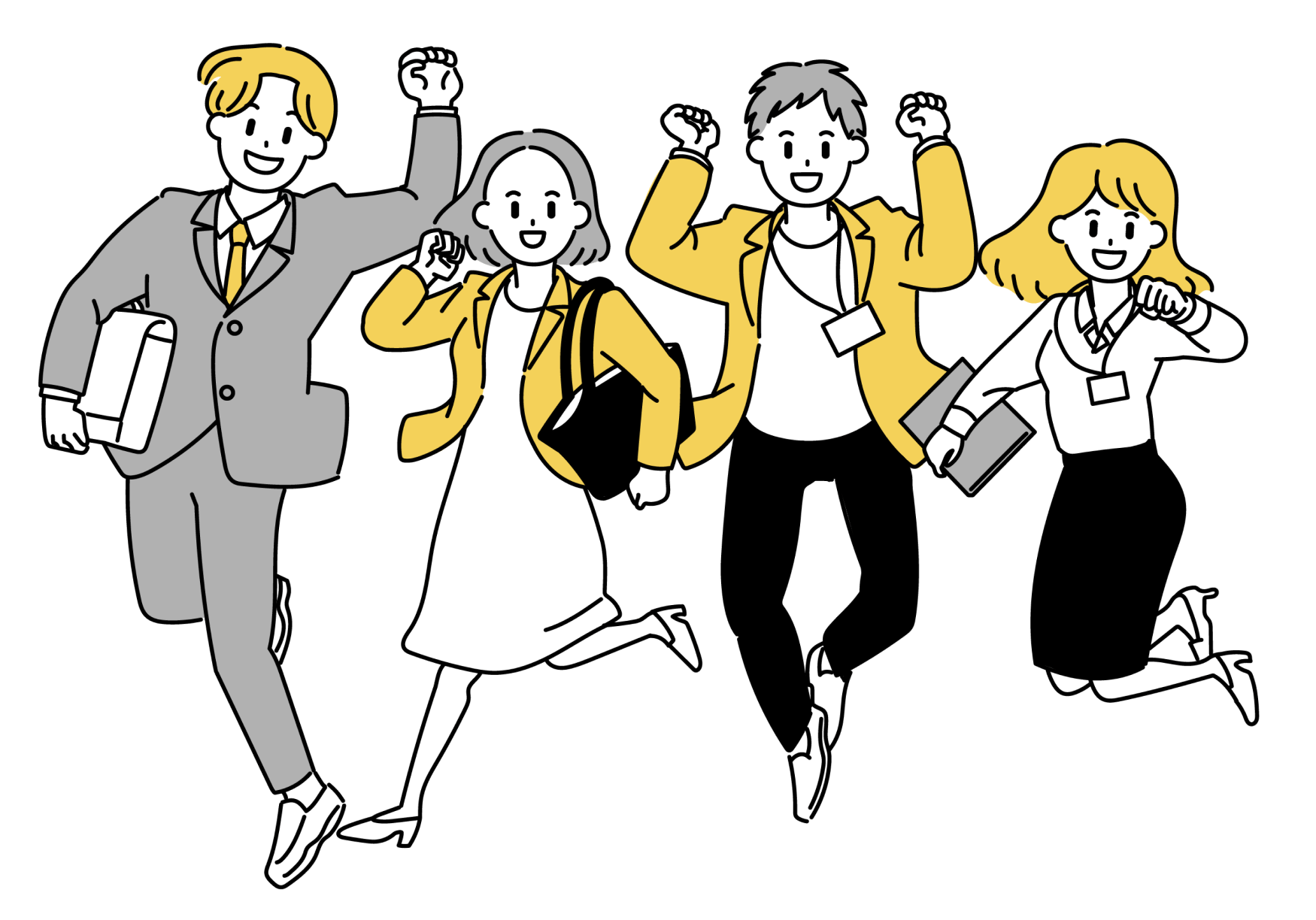お餅の工程を知ってみたら僕のサクセスストーリーにあまりにも似ていたので共有します

先日近所で餅つき大会があり、お手伝いで参加してきました!
張り切りすぎて筋肉痛ですw
出来立てのお餅は熱々で甘みがありとても伸びました。料理が趣味の僕は、家庭で手軽にできないか調べてみました。
餅つきの作業工程は、以下のようなステップで行われます。作り方は、伝統的な方法と現代の方法に分けられますが、ここでは伝統的な餅つきの工程を中心に説明します。
1. 材料の準備
– もち米の選定: 餅用のもち米(上新粉や白玉粉とは異なる)を用意します。
– 浸水: 餅米を約6〜12時間ほど水に浸けておきます。米がしっかりと水を吸うことが重要です。
– 蒸し器の準備: 再利用可能な蒸し器や竹製の蒸篭を用意し、水を入れて沸かします。
2. 蒸し作業
– 蒸す: 浸水したもち米を蒸し器に入れて、約30〜40分ほど蒸します。途中で水を足すことを忘れずに。
– 蒸し上がりの確認: 餅米がふっくらと蒸し上がったら、火を止めて取り出し、少し冷まします。
3. 餅つき作業
– 杵と臼の用意: 餅をつくために、杵(きね)と臼(うす)を用意します。臼には蒸し上がったもち米を入れます。
– つく作業: 杵で餅米をつきます。最初は軽くつき、徐々に力を入れていきます。この際、作業に参加する人が交代しながらつくことが一般的です。
– 「つく」: 杵で押しつける。
– 「まわす」: 餅を裏返し、均一にするために丸める。
– 「まぜる」: 餅のような粘り気が出るまで、十分に混ぜ合わせます。
コツはシンプルにスピードです!餅が冷めてしまうと米が残ってしまうからです。
4. 餅成形
– 餅を成形する: 完全についた餅を、大きな塊から小さなお団子状に分け、手で形を整えます。
– のしや型抜き: 餅を薄く延ばしたり、型抜きすることで、さまざまな形状の餅を作ることができます。
5. 餅の冷却・保存
– 冷ます: 成形した餅は冷まし、状態を整えます。
– 保存: 開けたばかりの餅は、同じ日に食べない場合、ラップや密閉容器に入れて冷蔵保存します。また、必要に応じて冷凍保存することも可能です。
6. 食べ方
– 餅の完成後は、あんこやきなこ、醤油や大根おろしなどと一緒に楽しむことができます。
この工程を通じて、家族や友人と共に作業をすることで、餅つきの楽しさとともに、伝統文化を体験することができます。
頑張って作ったお餅は最高に美味しかったです!
キャリカク小田原オフィスでも、頑張って作成した作業には深い喜びが生まれます。皆様で喜びの味を味わいませんか?☺
月別アーカイブ
- キャリカク小田原オフィスのワーク時間でAIを使用して究極の社歌を作成してくれました
- 正直者を毎年悩ませるあの日が近づいてきたので9割が知らなそうなルーツを調べた結果
- パソコン作業で疲労感を感じている方にマジでおすすめな解消方法をまとめてみました。
- スーパーで粋の良いイチゴをよく見かけ春を感じたのでイチゴについて深掘りしてみた
- ホワイトデーの意味を調べてみたらあまりにもホワイトだったので記事にしてみました
- 桃の節句は今日まで桃を食べる日だと思っていたのでちゃんと調べました。
- 横浜で三日間の実践研修を受けてきました。知識が深まりましたのでまとめてみました。
- 少しづつ暖かくなってきましたので恒例行事のあの事についてルーツを調べてみた
- 冬の花火大会は空気が澄んでいるのでとても鮮明で幻想的でした。感動したので
- もうすぐ4月なので、桜について調べてみたら実は綺麗な花だけではなかった件
事業所別ブログ
- キャリカクJR茨木駅前
- キャリカク一宮駅前
- キャリカク中村公園前
- キャリカク五日市
- キャリカク仙台八乙女駅オフィス
- キャリカク前橋駅前オフィス
- キャリカク勝川駅オフィス
- キャリカク北浦和事業所
- キャリカク古川駅オフィス
- キャリカク四日市駅オフィス
- キャリカク大分駅前
- キャリカク大垣オフィス
- キャリカク大阪なんば事業所
- キャリカク大須観音駅
- キャリカク小山駅
- キャリカク小田原オフィス
- キャリカク岐阜駅オフィス
- キャリカク岡山事業所
- キャリカク平安通
- キャリカク広島西
- キャリカク広島駅オフィス
- キャリカク東岡崎駅
- キャリカク津駅事業所
- キャリカク浅草橋オフィス
- キャリカク浜松駅前オフィス
- キャリカク甲府駅前
- キャリカク茗荷谷オフィス
- キャリカク藤が丘駅前事業所
- キャリカク藤沢南口
- キャリカク静岡駅